メモ。「作家にとっての作品は十全に準備された放たれた矢である(…)敏感な読者は確実に存在し、しっかり矢を受け止めている。しかし、それだけでは作家は闇夜に小さな的を目がけて矢を放つようなものだ。作家が弓を引き絞るために力を矯めるのを見守り、的に矢が当たりやすいように照明を工夫する人間がどれほどいるだろうか。そこで行き当たるのは批評の成熟の問題である」(桐野夏生)
5月。この4月は個人的に独特の緊張感を抱いて過ごした。200枚を超える小説を発表するのは久々で、新人賞の受賞1作目「来福の家」や、その後、7年以上もかかってどうにか心ゆくまでの形に仕上がった「真ん中の子どもたち」に続く「第3」のデビュー作を、日の目に晒すような心地でいたのだ。
不遜な言い方かもしれないが、私のあの作品をほんとうに必要としてくれる読者、敏感な読者はいるだろうし、今すぐではなくても、十何年も経ってから、ボロボロに擦り切れた色褪せた雑誌に載っている「祝宴」と題された作品を読んで「自分のためにこの小説は書かれたに違いない」と思う人もいるだろう。私が、私にとって大切な幾冊かの本や作家たちとそうやって巡り合えたように。
正直、「祝宴」を無事に書き終えられたことで、私は以前よりも強気でこうした可能性を信じられるようになった。
さらに遡って言えば、高村薫さんが「実に平凡な母娘の人生の微細な愛憎を端正な小説の言葉にしている」と『魯肉飯のさえずり』を評して下さったおかげで私は、記憶の中で疼くものを「小説の言葉にする」自分の筆力を、以前ほどは疑わなくなった。むしろ、書くことを望む限り、筆力を信じる責任が自分にはあるのだと思うようになった。「祝宴」はそのような心境の中で書いた作品だ。だからこそ、先日、担当編集者さんが届けてくれた読売新聞の文芸月評(2022/04/26付)では、私の創作の「土台」にまで言及してもらえたことに心底励まされた。

私は書くのも読むのも遅く、毎月届く文芸誌はほとんどが積読状態だ。表紙に躍る作家の名前や特集の組まれ方に興味を持ち、あとでゆっくり読もうと思っているうちに次の号が出ている。しかし今月は特別だった。とりわけ、自作も載る「新潮5月号」に、奈倉有里さんの「緊急報告」、無数の橋をかけなおすーーロシアから届く反戦の声ーーが載っていることには、大袈裟ではなく、何か救われるような思いがした。
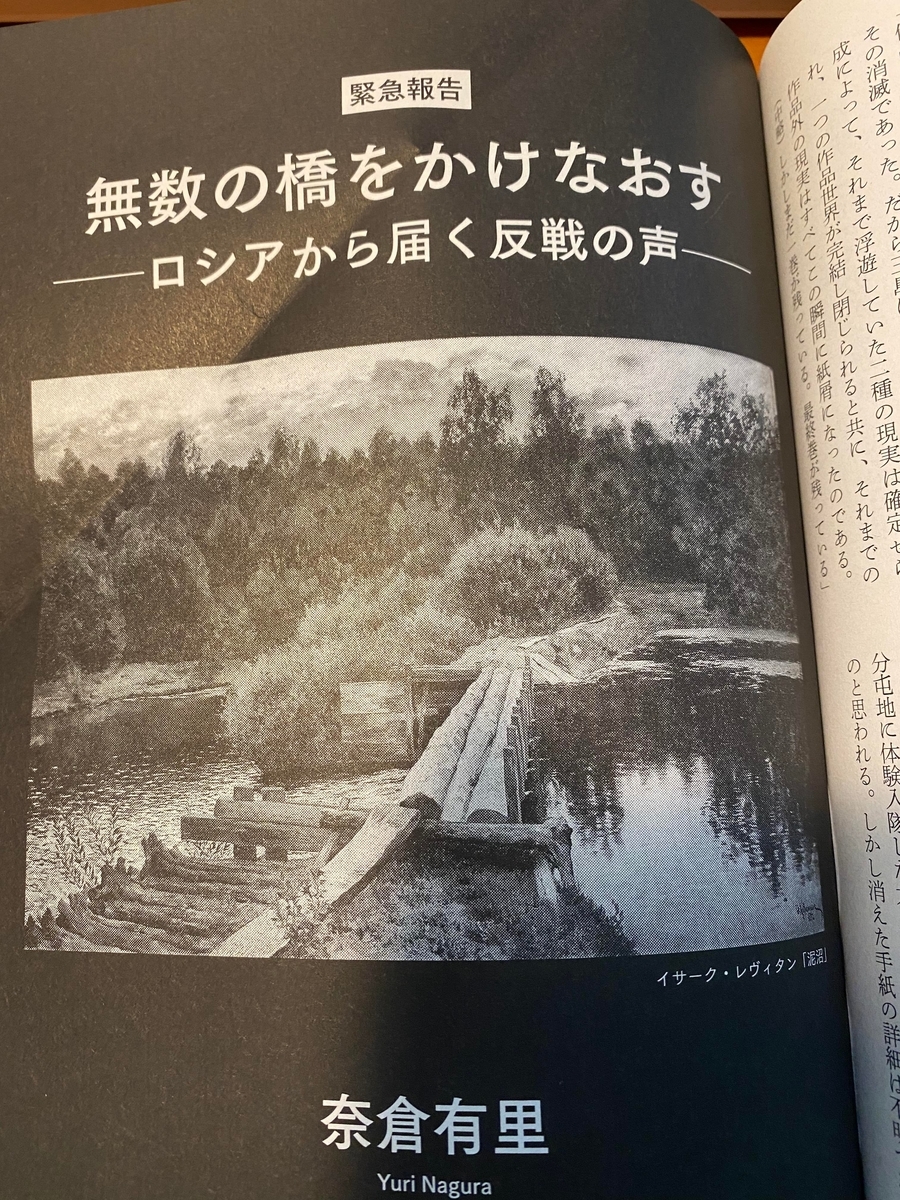
台湾海峡が封鎖されて、故郷に帰れなくなった両親。時代が変わって、両親にとって戻れなかった中国大陸は、台湾のビジネスマンにとって潤沢な市場となった。その商機に巧みに乗じて大成した一人の男が、最愛の娘との間に思いがけず生じた歪みにもがく…奈倉さんがお書きになる「無数の橋をかけなおす」という試みを、私もまた、あの小説を書くことで試していた気がしている。その意味では、やはりこの2022年4月に発売された「群像5月号」に、石沢麻依さんの小説「月の三相」があることにも、非常に勇気づけられた(しかも同号の「群像」には、その石沢さんが高橋たか子『亡命者』に寄せた批評も載っている。なんと画期的な編集なのだろう)。

石沢さんは42歳、奈倉さんは39歳、私は41歳で、そうであるからこそ余計に、自分と同世代かつ同性でもある「知識人」たちが、2022年を挟んだ前後半世紀以上の「世界地図」をそれぞれの角度から徹底的に意識し、その思考の過程を土台に、「圧倒的な暴力の前で」、「個の軌跡」とその「内面世界」を描く「使命」を備える文学の可能性をどのように信頼しているのか知るのは、私にとって大きな学びである。
創作は、その著者自身の現代世界に対する批評性抜きには成り立たないし、批評は、評する対象である創作物への根源的な尊重がなくては鋭くも深くもならない。文学が「絶対の自由に安らって」(高橋陽子)駆け続けるためには、創作と批評の充実が不可欠なのだと改めて思う。ちなみに、絶対の自由に安らって、は「群像5月号」に掲載された小説「川むこうの丘」より。あかるい嫉妬を燃やしたくなる表現にすっかり魅入られている。自由と安らぎのために、書く。「敏感な読者」のために、私も弓を引き続ける。