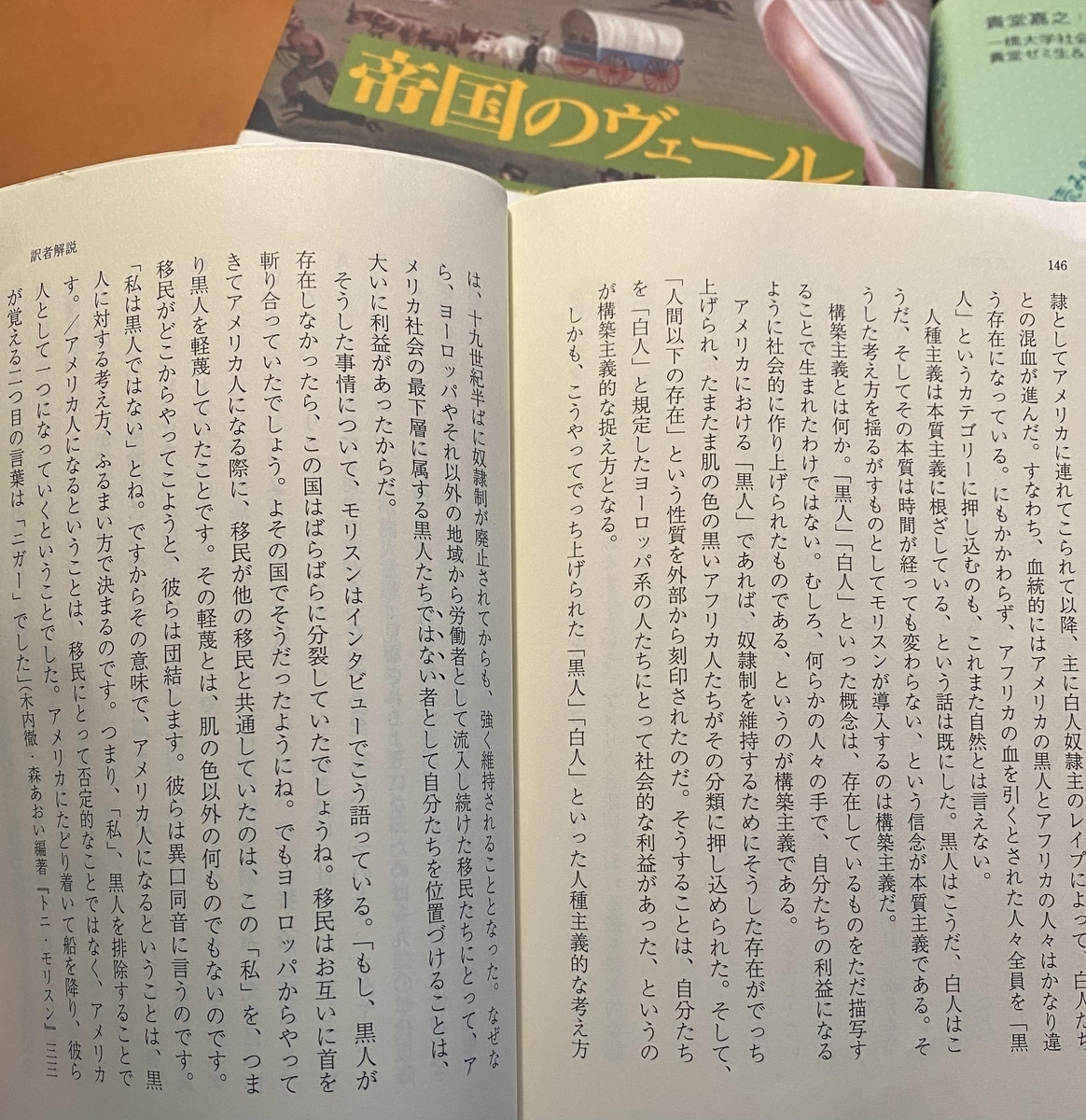メモ。「書くということは、『略歴』との戦いである。略歴を読んで納得するたぐいの『表現』は、『書かれたもの』の領域には入らない」(リービ英雄)
 1994年、リービ英雄は「最後のエッセイ」と題したエッセイにこう書きつける……「複数の答えを出すのに、どんな表現形式でもいいというわけではない。現状における『アイデンティティー』の必然的な複数性について、複数のエッセイを書いてみたところ、そのような答えを、エッセイのような形式、あるいは広い意味での『小説』以外の形式で模索する限界に、そろそろ気づきはじめたのである」。
1994年、リービ英雄は「最後のエッセイ」と題したエッセイにこう書きつける……「複数の答えを出すのに、どんな表現形式でもいいというわけではない。現状における『アイデンティティー』の必然的な複数性について、複数のエッセイを書いてみたところ、そのような答えを、エッセイのような形式、あるいは広い意味での『小説』以外の形式で模索する限界に、そろそろ気づきはじめたのである」。
私たちにとっては幸いなことに、『アイデンティティーズ』という魅惑的なエッセイ集に収録されたこのエッセイはリービ英雄の「最後のエッセイ」にはならなかった。リービ英雄はその後も小説だけでなく、極上の日本語で「非小説≒エッセイ≒?」も書き続けた。
2024年、私もまた、「アイデンティティーの必然的な複数性」を「『小説』以外の形式で模索する」ことによって育んできたつもりの、自分なりのこの「土壌」で、もう一度、この些細な「略歴」を遥かに上回る「表現」を目指して、新たな小説を書く意欲を感じている。
次こそ、長篇を。
リービ英雄よりもちょうど30年遅く生まれた私の、これからの数年間は、この「挑戦」のために費やされるだろう。いつかの自分が、今日のこの覚悟を懐かしく思い出せますように。